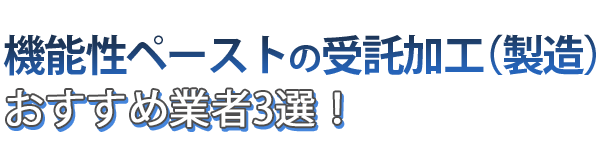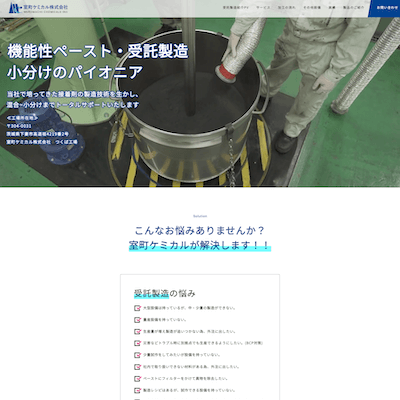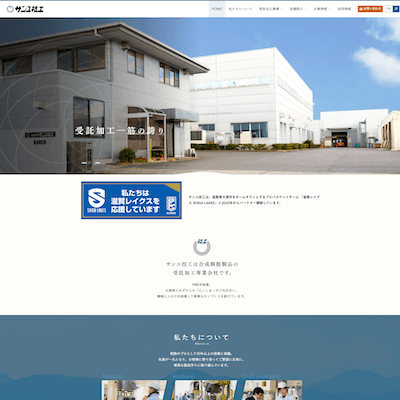エポキシ樹脂という言葉を聞いたことがありますでしょうか?エポキシ樹脂には強力な接着力があるため、さまざまな素材の接着剤として利用されています。聞いたことはあるがエポキシ樹脂はなぜ強力なのか理由を知りたい、という方も多いのではないでしょうか。ここでは、エポキシ樹脂の基本的な性質と硬化反応について、詳しく紹介します。
エポキシ樹脂とは?
エポキシ樹脂は、複数の優れた耐性を持つ熱硬化性樹脂の一種です。産業用から民間用まで、広く利用されている化合物です。基本的な性質
分子内に2個以上のエポキシ基を持つ化合物の総称がエポキシ樹脂です。硬化剤と混ぜ合わせて加熱することで硬化する性質の、熱硬化性樹脂です。加熱すると軟化し、冷やすと硬化する熱可塑性樹脂とは、性質が異なります。優れた耐性
高い電気絶縁性により、電子基板や電子材料にも使用されています。電気絶縁性とは、電気を通しにくい性質のことで、電気を遮断し漏電を防ぐ働きがあります。硬化剤の種類やプレポリマーとの混合により分子量を調整することで、さまざまな特性を引き出すことができます。エポキシ樹脂の硬化反応メカニズム
エポキシ樹脂は、硬化剤と化学反応を起こすことでネットワーク構造を形成します。硬化反応のメカニズムと主な反応タイプについて解説します。硬化反応のメカニズム
エポキシ樹脂の硬化反応は、エポキシ基と硬化剤が化学反応を起こしてネットワーク構造を形成するメカニズムです。エポキシ樹脂に硬化剤を混合し加熱すると、橋を架けるように高分子同士が結合する架橋反応が起きます。架橋反応によって高分子の物理的・科学的性質が変化し、化学構造が強固になります。高分子とは、分子量が非常に大きく多数の原子が繰り返し結合して連鎖状につながった分子を指します。
架橋反応は一方向にしか反応しないため、一度架橋が形成されるとエポキシ樹脂に熱を加えても液体には戻りません。混合する硬化剤の種類や量などが、硬化物の特性に影響します。そのため、用途や使用方法に適した硬化剤を選択することが重要になります。
酸無水物系硬化
酸無水物系は電気絶縁性や耐熱安定性に優れているため、電気・電子絶縁材料として一般的に使用されています。酸無水物との化学反応により、熱硬化するタイプです。イミダゾールは、エポキシ樹脂と酸無水物の反応を促進する硬化促進剤です。酸無水物の多くは低粘度なので、混ぜ合わせやすい特徴があります。フィラーを合わせることで高い耐熱性を付与できるため、半導体実装などとして広く利用されています。
アミン系硬化
エポキシ樹脂の一般的な反応タイプです。硬化剤に用いられるアミンは、脂肪族や芳香族、変性など種類が多く、用途・使用条件に応じて使い分けられます。シリコーン系硬化
シリコーン系は、柔軟性・耐油性に優れているゴム状の接着剤です。シリコーンポリマーを主成分とし、加水分解や酸触媒で架橋硬化するタイプです。エポキシ樹脂の高い接着力とシリコーン樹脂の柔軟性・耐熱性などの特性を兼ね備えています。チオール系硬化
反応性の高さから、常温での硬化も可能です。低温でも速硬化する特徴があるため、さまざまな分野で利用されています。フェノール系硬化
エポキシ樹脂と硬化剤としてフェノール樹脂を混合した接着剤です。強い接着力があり、耐薬性・耐熱性・電気特性に優れています。カチオン重合系
カチオンとの重合によって硬化するタイプです。アウトガスが少なく硬化収縮も小さい傾向があるため、精密部品の接着に適しています。エポキシ樹脂接着剤の主な用途と選ばれる理由
エポキシ樹脂接着剤は、幅広い分野で活用されています。主な用途と選ばれる理由について解説します。接着剤
エポキシ樹脂は、混合する硬化剤の種類や接着する素材によって硬化物にさまざまな耐性を付与できる特徴があります。そのため、金属やガラス、コンクリート、木材など、多種多様な素材の接着が可能です。用途や目的に応じた接着剤が開発されており、適応性の高さなどから、さまざまな素材の接着に向いています。電子工学機器の封止材
封止材には、電子部品を衝撃や熱、湿度、ホコリ、化学物質などの外部環境から保護する役割があります。電子部品の封止材には、電気絶縁性や耐熱性が欠かせません。半導体パッケージやプリント基板、電子回路などの封止・接着・絶縁にエポキシ樹脂が用いられています。硬化剤との組み合わせにより、用途に適した接着剤を開発できるのが特徴です。