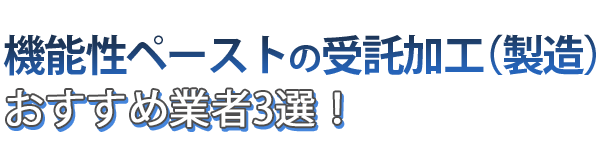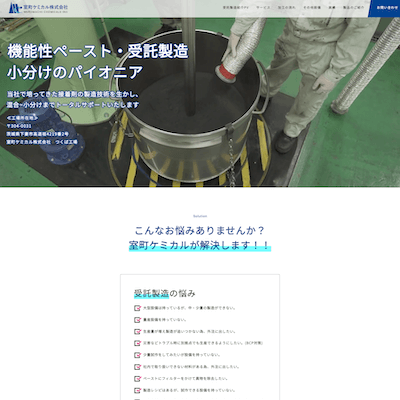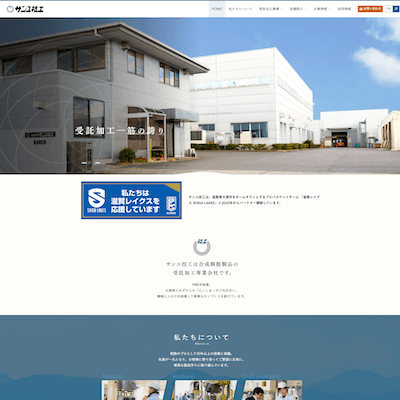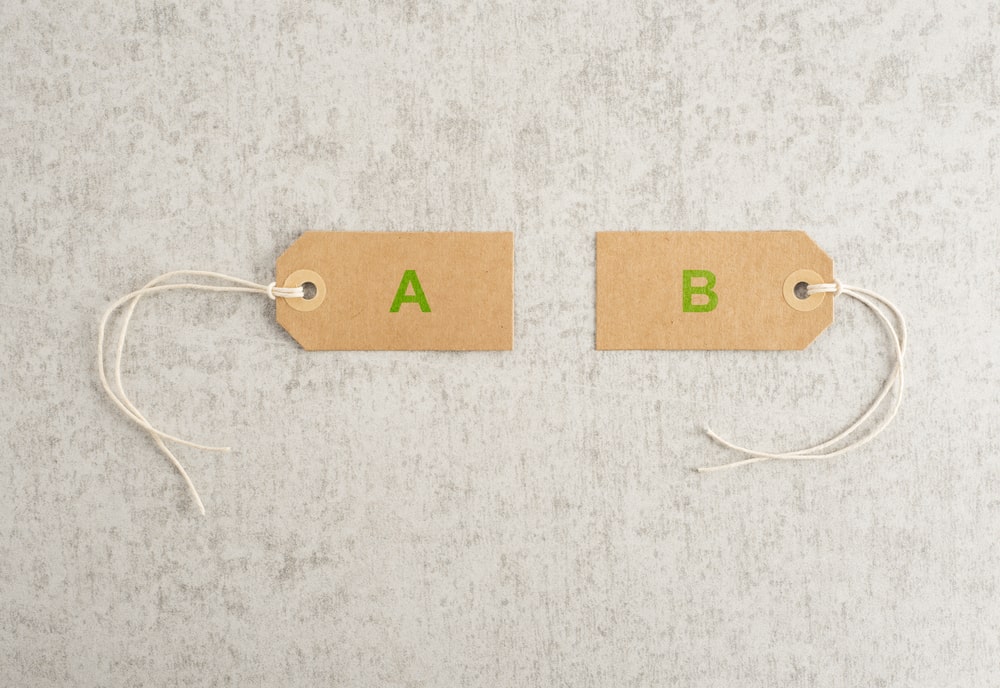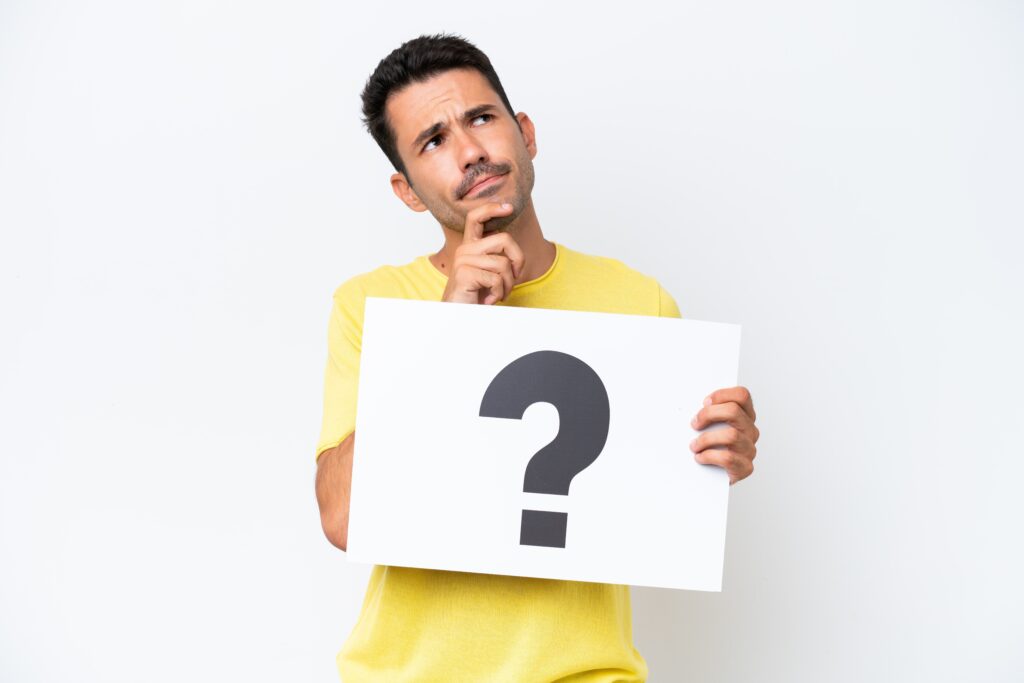仕事や日常生活で接着剤を使用するケースもあるでしょう。ただ、ひとえに接着剤といっても、さまざまな種類があり、どれを使用すればいいかわからない方も多いのではないでしょうか。そこで、今回は接着剤の種類と特徴を解説します。さらに、種類別の用途も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
接着剤の基本分類とは?
接着剤は、成分や硬化の仕組みによっていくつかの種類に分類されます。まず、分類のひとつの軸となるのが主成分や溶媒の違いです。接着剤にはおもに水性系、溶剤系、化学反応系、ホットメルト系といった種類があり、それぞれ特徴が異なります。水性系接着剤は、水を溶媒として使用しており、代表的なものに木工用ボンドや紙用接着剤などがあります。水分が蒸発することで接着剤が硬化する乾燥硬化タイプに分類され、環境負荷が少なく、扱いやすいことが特徴です。
ただし、水や湿気に弱いため、使用環境には注意しましょう。一方、溶剤系接着剤は、有機溶剤に樹脂成分を溶かした接着剤です。乾燥によって溶剤が揮発し、接着剤が固まります。
大きな分類では乾燥硬化タイプですが、水性系に比べて接着力が強く、幅広い素材に対応可能です。ただ、溶剤の刺激臭や引火性、作業環境への影響を考慮する必要があります。
また、化学反応系接着剤は、2種類の成分を混合することで化学反応を起こして、接着力が向上するタイプです。エポキシ系やウレタン系などが代表的で、硬化後は非常に高い強度と耐久性をもちます。
硬化には「化学反応」が必要で、物理的な乾燥ではなく、分子レベルでの構造変化が起きるため、過酷な環境下でも優れた性能を発揮します。そのほか、ホットメルト系接着剤は、熱を加えて一旦溶かし、冷却することで固まる接着剤です。
スティック状の接着剤をグルーガンを使って塗布し、溶剤が冷えると固まるのが特徴です。乾燥時間がほぼ不要で作業効率が高いといったメリットがあります。
ただし、高温に弱い素材には適さないことがあります。接着剤は使用目的や素材、環境に応じて、成分や硬化方法を理解し、最適なタイプを選ぶことが重要です。
水性系接着剤の種類と特徴
水性系接着剤は、水をおもな溶媒として使用する接着剤で、環境負荷の低さや安全性の高さから、近年さまざまな分野で注目を集めています。水分が蒸発することで硬化する乾燥硬化タイプが一般的で、有機溶剤をほとんど使用していないか、最小限に抑えられているので、揮発性有機化合物の排出が少なく、臭気や中毒リスクが低いという点が大きな特徴です。
また、水性接着剤の中でももっともポピュラーなのが、酢酸ビニル樹脂を乳化させたPVA系接着剤です。一般的には「木工用ボンド」として知られ、木材、紙、布など多孔質の素材に優れた接着性を発揮します。
乾燥後は透明になるタイプが多く、価格も安価で使いやすいので、DIYや事務用途から学校現場まで広く使われているのが特徴です。ただし、水に再び濡れると強度が低下するという弱点があるので、耐水性が求められる用途には不向きです。
また、水性系のアクリル系接着剤は、外壁材、フローリング、断熱材などの建築材料にも使用されており、建材用の環境対応型接着剤としての需要が高まっています。
アクリル系は接着後の柔軟性があるので、振動やひずみのある部分で柔軟性を維持できるのが特徴です。ホルムアルデヒドなどの有害物質を含まないF☆☆☆☆認定製品も多く、住宅の室内空気環境対策としても評価されています。
そのほか、ポリウレタンを水中に分散させたタイプもあり、強い接着力と耐水性、耐熱性を兼ね備えているものも少なくありません。防水シートの貼付や床材の施工など、建築・土木分野での用途が広がっている高機能水性接着剤です。
溶剤系ウレタン接着剤と比較して安全性が高く、作業環境にも優しい点が評価されています。近年の建築業界では、環境にやさしい接着剤であることに加え、高い性能をもっていることの両立が求められています。
従来は性能面で不利とされていた水性接着剤ですが、技術の進化によって高性能化が進み、アクリル系やポリウレタン系を中心に、建材用途への本格的な展開が可能になりました。F☆☆☆☆やグリーン購入法適合などの認証を取得した製品も増えており、公共建築や環境配慮型住宅にも採用されています。
なお、ユリア樹脂接着剤は、尿素とホルムアルデヒドを主成分とする樹脂をベースにした接着剤で、木材加工ではもっとも広く用いられています。硬化が速く、接着力に優れ、コストが安いという利点から、合板やMDF(中密度繊維板)、家具の芯材などに広く使用されているのが特徴です。
ただし、水や湿気に対する耐性が比較的弱いので、屋内用の非耐水製品に多く用いられるのが一般的です。ホルムアルデヒドを含むため、F☆☆☆☆規格などの低ホルム製品を選ぶことで、室内空気質への影響を抑える対応が進められています。
また、メラミン樹脂は、メラミンとホルムアルデヒドを反応させたもので、ユリア樹脂よりも高い耐水性と耐熱性を備えています。このため、水回りや高湿度環境、耐熱性が求められる、キッチンカウンターや浴室などの木質建材に多用されます。
また、メラミン樹脂はユリア樹脂との共重合体として使われることも多く、加工性やコストとのバランスを取った製品が豊富です。高い安定性や硬化後の耐久性により、耐候性が必要な用途にも適しています。
フェノール樹脂は、フェノールとホルムアルデヒドの縮合によって得られる熱硬化性樹脂で、接着剤としての歴史も古く、現在でも構造用合板や耐水構造材など強度と耐久性が求められる用途で重要な位置を占めています。
フェノール樹脂接着剤の最大の特徴として挙げられるのが、優れた耐水性・耐熱性・耐久性です。屋外構造材、橋梁や土木構造用合板など、長期間にわたって厳しい環境にさらされる用途に適しています。
硬化時に暗褐色となるため、外観を重視する家具や内装には不向きですが、構造材としての信頼性は高く、建築基準法上の認定合板などにも採用されています。
高機能が求められる化学反応系・溶剤系接着剤の用途
産業用や建設現場、輸送機器、電子機器の製造など、高い強度・耐久性・耐環境性が求められる現場では、汎用接着剤では性能が不十分なことがあります。こうした場面で活躍するのが、化学反応を利用して硬化する「化学反応系」や、有機溶剤に樹脂を溶解させた「溶剤系」の高機能接着剤です。中でも、エポキシ系接着剤は、エポキシ樹脂と硬化剤を混合することで化学反応を起こし、高い接着強度を実現します。硬化後は硬く強固な接合体となり、機械的負荷にも耐えられるので、金属・セラミック・炭素繊維などの高機能材料の接合に適しています。
また、ウレタン系接着剤は、ポリオールとイソシアネートの反応によって硬化し、柔軟性と強度、耐衝撃性のバランスに優れた接着剤です。硬化後も弾性をもつので、振動や衝撃を受ける構造物の接着や複合材料の接合に適しています。
そして、変成シリコーン接着剤は、シリコーン樹脂の柔軟性と、ポリウレタンの接着力を兼ね備えたハイブリッド系の高性能接着剤です。湿気と反応して硬化する一液型が主流で、施工性がよく、シーリングと接着を兼ねた製品が多くあります。
ホットメルト接着剤の特徴と応用分野
ホットメルト接着剤とは、熱で一時的に溶かし、冷えることで固化する性質があります。常温では固体の状態で保存され、加熱によって溶融し、接着したい対象物に塗布された後、冷却されることで瞬時に接着が完了します。速乾性に優れており、スピード重視の製造現場で幅広く使用されています。包装や製本、電子機器など、さまざまな製品に使用されているのが特徴です。