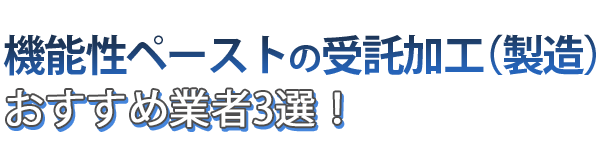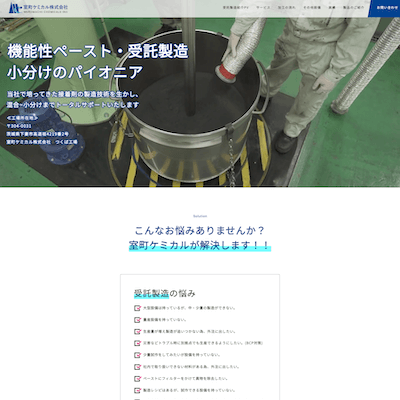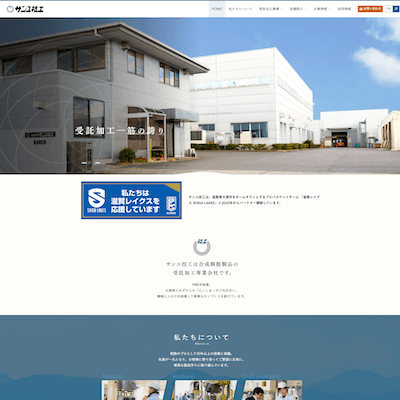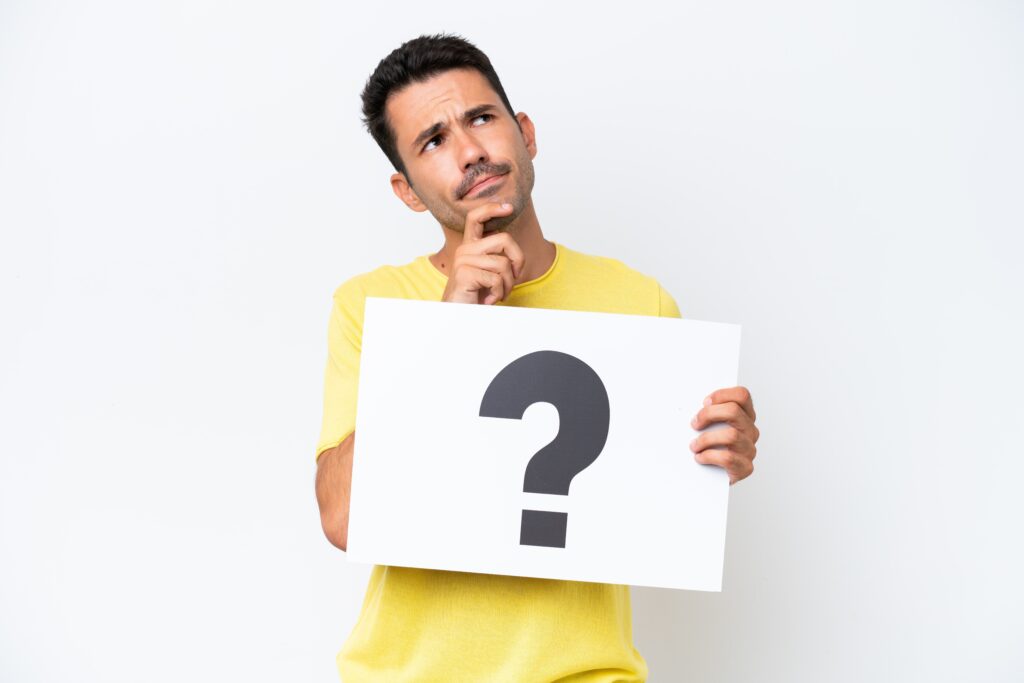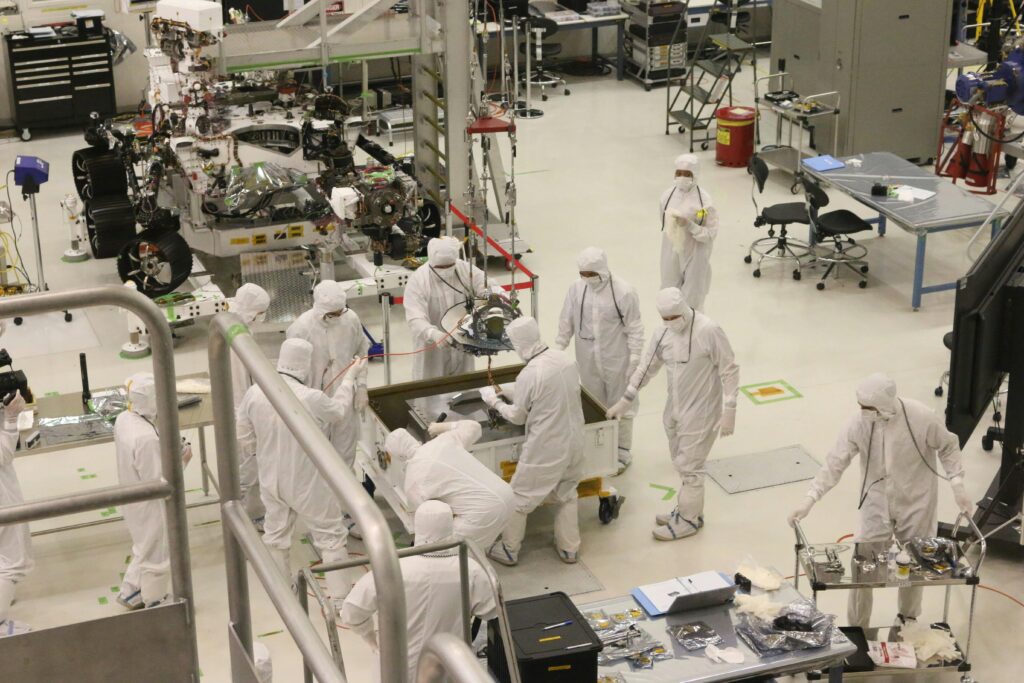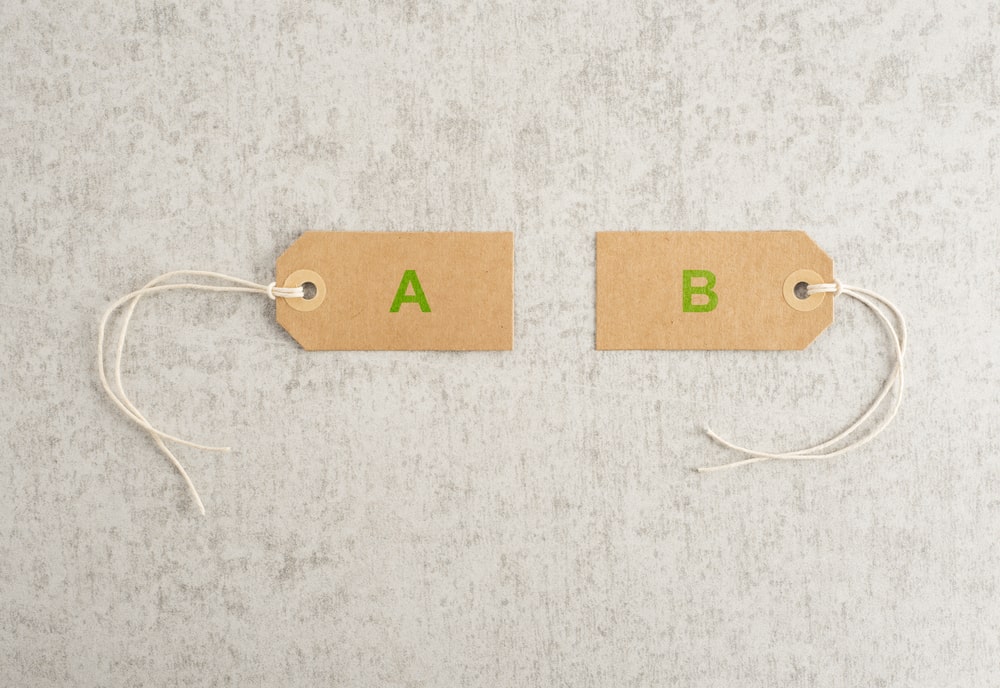導電性ペーストは、はんだとは異なる特性をもっており、さまざまな用途で広く活用されています。ただし、使い方を誤ると性能が十分に発揮されないこともあるため、注意が必要です。この記事では、導電性ペーストの基本的な特徴や種類、使用方法、注意点についてわかりやすく解説します。
導電性ペースト(銀ペースト)とは?
導電性ペーストは、電気を通す微細な金属粒子を樹脂に分散させた接着剤の一種で、銀を主成分とするものは銀ペーストと呼ばれています。低温での加工が可能なため、熱に弱い素材や特殊な材料との接合に適しています。はんだとの違い
はんだと同様に電気的接続を果たす役割をもつ導電性ペーストですが、その成分や硬化方法には大きな違いがあり、適用される場面も異なります。とくに、材料選定の自由度や加工の柔軟性において、導電性ペーストには独自のメリットがあります。はんだの場合、熱を加え金属同士を溶かして結合させます。導電性ペーストは、加熱温度がそれほど高くなくても固まるため、温度に敏感な部材の接合にも使えるというのが利点です。
接着の仕組みとしては、導電性粒子を含んだ樹脂が硬化して物体同士を結びつけるため、金属表面の酸化被膜の影響を受けにくくなっています。
また、はんだは一度溶かして接合するため、再加熱時に再溶融してしまうリスクがあります。それに対し、導電性ペーストは硬化した樹脂が接着剤の役割を果たすことで、基材と一体化するため、再加熱しても溶けることはありません。
選ばれる理由
これまで電子部品の接合では、おもにはんだが使われてきました。近年は機器の小型化や柔軟性の要求が増し、熱に弱い素材の採用が増加しています。その結果、従来の高温処理では対応が難しい場面が多くなっています。導電性ペーストは、比較的低温で硬化できることから、そうした熱に敏感な部材にも無理なく適用できるのが大きな特長です。こうした性質が注目され、とくにフレキシブル回路やウェアラブル技術の分野で、採用が急速に進んでいます。
導電性ペーストの種類と特徴
導電性ペーストは、いくつかの種類が存在します。それぞれの特性を理解し、用途に合ったものを選ぶことが重要です。熱硬化型と乾燥型の違い
熱硬化型の導電性ペーストは、熱を加えることで樹脂がしっかりと固まり、強力な接着力を発揮します。このタイプは接着強度や電気伝導性が高いため、精度が求められる電子部品などに広く使われています。一方で、乾燥型のペーストは、含まれる溶剤が蒸発することで固まり、導電性を発揮します。熱硬化型ほどの強度はありませんが、常温で処理できる利点があり、耐熱性のない素材にも使用することが可能です。
代表的なTKペーストの特性
一般的な接着剤は電気を通さず、絶縁性をもっているのが普通です。これに対して導電性ペーストは、エポキシなどの有機樹脂に銀やカーボンなどの導電性粒子を均一に分散させた構造になっています。硬化時には粒子同士がつながり、電気がとおる経路が自然に構成され、導電性が発生します。用途に応じた選び方
導電性ペーストに使用される樹脂や導電材料にはさまざまな種類があり、性能もコストも製品ごとに異なります。そのため、最適な組み合わせを選ぶ必要があります。もっともよく使われているのはエポキシ樹脂系の熱硬化型で、とくに銀を使ったものは酸化しにくく、安定した電気伝導性をもっているため、電子機器で多く採用されています。
導電性ペーストの正しい使い方
導電性ペーストの性能をしっかり引き出すには、適切な使用手順と保管管理が欠かせません。ここからは、塗布から硬化、保存までの基本的な取り扱い方法を紹介します。塗布から硬化までの手順
接着面に汚れや油分が残っていると性能に影響を及ぼすため、使用前には溶剤でていねいに掃除しておく必要があります。ペーストの塗布には、量を正確に調整できるディスペンサーを使用すると便利です。熱硬化型の場合は、メーカーが指定する温度と時間で恒温オーブンによる加熱処理を行います。乾燥型は、溶剤がしっかり揮発するように設定された温度環境で乾燥させてください。
導電性を確保するための温度管理や混合・乾燥のコツ
作業する環境の温度・湿度は導電性ペーストの性能に影響を与えることがあります。理想的な作業温度は25℃以下とされており、作業時は空調管理にも注意しましょう。また、オーブンでの乾燥条件によって硬化の状態が変化するため、作業前に条件を確認しておくことで、トラブル防止につながります。
安全な取り扱いポイント
導電性ペーストは一般的に冷凍状態で出荷されることが多く、使用前も冷凍庫での保管が必要です。とくに再冷凍や再解凍は避けてください。これにより水分や異物が混入し、性能低下の原因になります。一度解凍したペーストは、なるべく早めに使い切るようにし、保管ルールを守ることが、安定した性能を保つためのポイントです。また、取り扱いの際には手袋や換気設備の使用も推奨されており、安全性への配慮も欠かせません。